障害年金の対象となる傷病というと、肢体障害(手や足の障害)、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は心臓病や肝臓病、糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、癌などの内部疾患や精神疾患といった様々な傷病が対象となります。
次に障害年金の対象となる主な傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。
視覚
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症、糖尿病性網膜症 など
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく嚥下、音声または言語
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工骨頭、上下肢の離断又は切断など
脳血管疾患
脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など
精神疾患
統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害、高次脳機能障害など
呼吸器疾患
ぜんそく、気管支ぜん息、肺線維症、肺結核、肺線維症など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症、心臓弁膜症、解離性大動脈瘤など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝臓ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他、血液、造血器疾患
悪性新生物(ガン)、化学物質過敏症、強皮症、シェーグレン症候群、パーキンソン病、悪性リンパ腫、その他の難病など
このように様々な傷病があり、また、複数の傷病を併発している場合もあるため、実に様々な症状があります。
ご自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
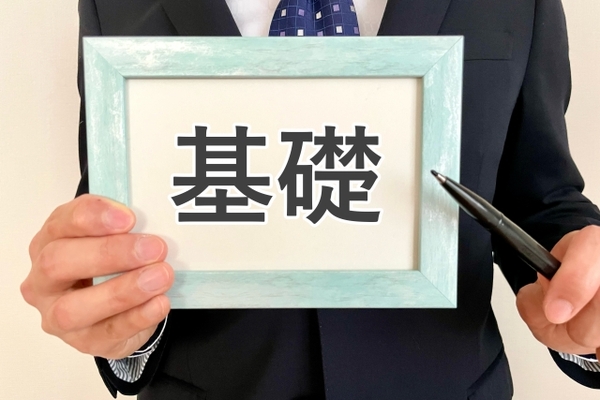
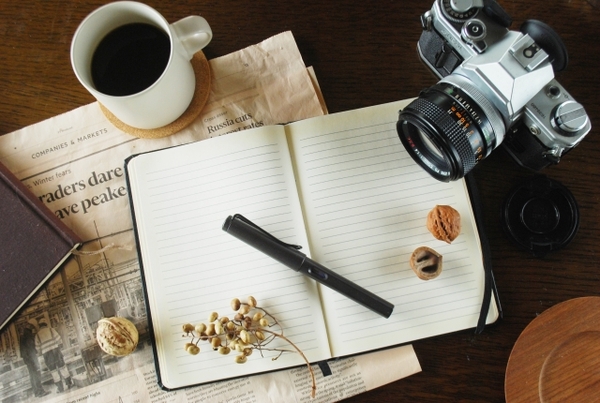



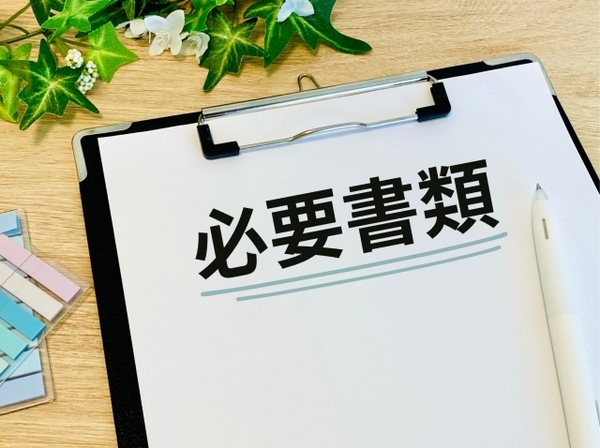



 03-5919-1150
03-5919-1150 080-5880-2563
080-5880-2563